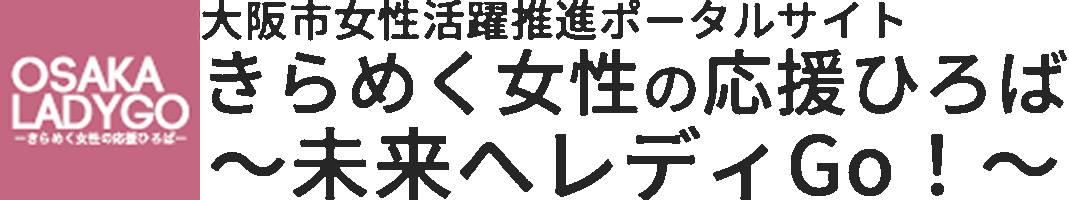2025年7月9日、大阪・関西万博ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartier 「WA」スペースにて、世界に向けて女性たちの挑戦や想いを発信する取り組み「グローバルプレゼンテーション」が開催されました。
この場には、地域や世界の課題に立ち向かう女性たちが登壇。
自らの活動を通して、未来を切り拓く姿を発信しました。
その中で本記事では、その登壇者のひとりである津田久美子さんのストーリーをご紹介します。
アフリカ・ルワンダを舞台に「生理の貧困」というテーマに取り組む津田さんは「行動を起こすのに年齢や経験は関係ない」と語ります。
立ち上げに至った思いやこれまでの挑戦、今後の展望をぜひお読みください。
目次
- 津田さんの活動内容と、その活動を始められたきっかけについて教えてください。「生理の貧困」というテーマに出会い、取り組もうと思われたのはなぜですか?
- NGO団体Gift of Bananaでの現地での反響や変化はどんなところに感じますか?
- ルワンダという異国で活動する中で、一番苦しかった壁はどのようなものですか?それを乗り越えられたきっかけは何でしたか?
- 仕事と家庭の両立やバランスの取り方で、心がけていること・大事にしている考えはありますか?
- 今回、大阪・関西万博のウーマンズ パビリオンでグローバルプレゼンテーションに参加をされますが、どんな想いでこの機会に臨まれますか?
- Gift of Bananaとして、今後さらに広げたい挑戦・夢を教えてください。
- 今これから何かを始めたいと思っている大阪市の女性たちヘエールをお願いします
津田さんの活動内容と、その活動を始められたきっかけについて教えてください。「生理の貧困」というテーマに出会い、取り組もうと思われたのはなぜですか?
私がアフリカで支援活動をスタートしたのは、2000年頃のことです。
エチオピア大使館での勤務を通して初めて知ったエチオピアの現状。当時コーヒー危機で苦しんでいたコーヒー農民を支援するため、NPO法人を立ち上げました。
その後、日本へのエチオピア・
自給自足の生活で、雇用機会が殆ど無い現地の人達が収入を得られるように開始したのが「バナナ・ペーパープロジェクト」でした。
地域一帯を覆い尽くすバナナの木々、実を採った後に捨てられる茎から何か作れないか?と考えたのです。
現地でスタッフ達と一緒に作るバナナペーパー。
日本では触れる機会の無かったバナナ茎の内部構造を知るうちに、内皮・中皮・外皮の各層が樹液をストップしている事に気づきました。
そんな折り、スタッフ達から「生理ナプキンを買えないため、毎月困っている人が沢山いる」と聞きました。そこで、バナナの皮を使ってナプキンを作ってみようと思いつき、サンプルを作り試用してもらうことにしました。
しかし現地では材料を調達できず、プロジェクトとして実施するまで少し時間がかかりました。その後、コロナ禍でバナナペーパー・プロジェクトは中断。現地訪問も叶わなくなりましたが、その時間に改めてナプキンセットの改良に取組み、2022年秋にようやく「バナナ布ナプキン・プロジェクト」を開始することができました。

NGO団体Gift of Bananaでの現地での反響や変化はどんなところに感じますか?
そこで一人でも多くの生徒にナプキンを届けるため、北部ルリンド郡の教育課と協働し、学校で教師にバナナ布ナプキンの作り方を教えてもらうことにしました。「ただ嘆くのではなく、生徒自らが自身のナプキン・セットを作り、自分で解決しよう!」と訴えた結果、多忙な教師達も時間を見つけて教えてくれる様になり、第一期は15校、約3,000名の生徒達が参加しました。
「バナナ布ナプキン・セット」とは、
- ナプキン(ネル生地)
ナプキンの形に縫うのではなく、洗いやすく、乾きやすい様に、中心が9枚になる様「畳み方」を教えます。 - バナナ皮
ストッパーとしてナプキンの下に置きます。 - ホルダー
バナナ皮がずれない様にホルダーにセットし、下着にホックで装着します。 - ケース
使用前そして使用後の双方のナプキンを入れるケースです。
現在、第二期30校、約5,000名の生徒達にナプキンの作り方を伝えています。作り方を学んだ生徒達は姉妹や友達、そして周りのコミュニティヘも伝え始めています。また教師からの報告では、男子生徒も交えてナプキン作りを教える学校もあるとのことでした。
ルワンダでは一部ホテルやキガリのレストラン、役所などを除いて、特に地方のトイレは汲み取り式です。学校のトイレは男女別に分かれていないため、使用済みナプキンを入れる容器を置くことができません。
さらに、ゴミの収集システムが整備されていないという問題があります。化学薬品を使用した紙ナプキンは、トイレに破棄されても自然に分解されないため、今後その使用量が増えることで、環境問題ひいては社会問題に発展しかねません。
そのために、教師達を集めて作り方を説明する「セッション・ミーティング」では、環境汚染の問題についても訴えています。
有り難い事に校長達から「作り方を教える時に、生徒達に環境についても教える様にする」などのレポートが届きました。

文化·習慣の違いもあり、
こうした違いも私の場合は殆ど問題にならず、
ルワンダという異国で活動する中で、一番苦しかった壁はどのようなものですか?それを乗り越えられたきっかけは何でしたか?
現地に駐在できず、また長期滞在も難しい状況の中で、現地スタッフへの長期的な依頼を行うことが困難でした。そのため、当初は年に2~3回訪問を繰り返し、メールでのやりとりを通じてプロジェクトを進めていましたが、そのやりとりも途絶えることもあり思うように進められない経験もしました。
しかし、「バナナ布ナプキン・プロジェクト」を開始する際は、バナナペーパーの実績を評価していただき、郡の教育課と協働が叶い、開始から3年目が経ちましたが、教育課の役人や教師達とのコミュニケーションは、比較的スムーズに進められています。
仕事と家庭の両立やバランスの取り方で、心がけていること・大事にしている考えはありますか?
私がルワンダを初めて訪れたのは2008年、60歳の時でした。それから17年が経ちましたが、私がルワンダを訪問する約2週間は、主人は日本でプロジェクトの進展を見守ってくれていますので、連携をとりながら進めています。
今回、大阪・関西万博のウーマンズ パビリオンでグローバルプレゼンテーションに参加をされますが、どんな想いでこの機会に臨まれますか?
「生理の貧困を解決するために紙ナプキンを贈呈する」という物質的な支援ではなく、材料費を学校毎に提供し、自分達で工夫して「生理ナプキン」を作るという技術的な支援を行いました。
ですから、「自分で生理ナプキンを作ることができる」という自信と、生理になっても安心という精神的な安堵に繋がればと考えています。
周囲からの差別を、自ら工夫して乗り越えてほしい、また、明るく健全な学校生活を送ってほしいと訴えていきたいです。
Gift of Bananaとして、今後さらに広げたい挑戦・夢を教えてください。
まずはルワンダのルリンド郡内にある全116校で「バナナ布ナプキン・プロジェクト」を実施したいと考えています。
現在、実施済みの45校に加えて、本年10月訪問の際に30校での実施を予定しており、計75校となります。全校達成まで頑張りたいと考えています。
その後、彼ら自身がこのプロジェクトをどの様に拡げていくか、応援しながら進めたいと思います。

今これから何かを始めたいと思っている大阪市の女性たちヘエールをお願いします
関西万博が開催され機運が熟しておりますが、大阪市にはこれを機に思いをカタチにされたい方は多くいらっしゃると思います。
そこで、世界へと一歩踏み出されたご経験から、今これから何かを始めたいと思っている大阪市の女性たちヘエールをお願いします。
私の活動は、「支援を始めよう」という思いが全てのスタートでした。
現地のニーズを知り、軌道修正しながら粘り強く続けることが大事だと思います。
私の場合、子育ても一段落した50代の時、エチオピア大使館での勤務から世界へ視野が広がり、NPO法人を立ち上げました。
いくつもの壁にぶつかりましたが、周囲の人達に支えられ今日まで来ました。
コーヒーについても紙づくりについても全くの素人で、勉強したことはありませんでした。
行動を起こすのに、年齢や経験は関係ありません。
知識が必要であれば、その時に学べばいいと思っています。
日本に閉じこもるのではなく、世界から色々なものを吸収して成長していただきたいと思います。
NPO法人Gift of Banana代表。
年子3人の子育てが一段落した40歳で大使館勤務を開始し、50歳でエチオピア大使館へ。
アフリカ農民支援を進める中でルワンダで都市と地方の格差や「生理の貧困」という課題に直面する。
廃棄されるバナナの茎から防水性の高いバナナ皮を活用し、バナナ布ナプキンを考案。
現地の学校と連携し、教師が生徒に作り方を教える仕組みを広げて女性の衛生環境を改善する。
HP:http://hat.site-omakase.com/