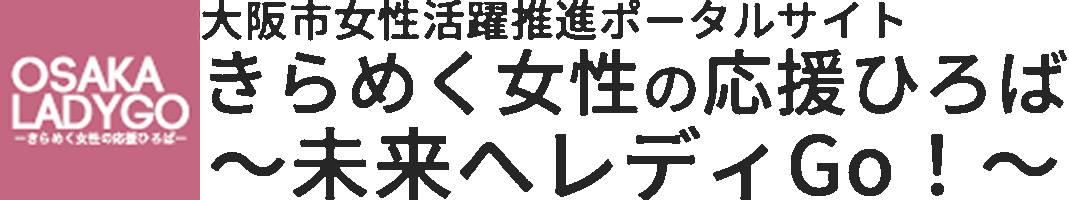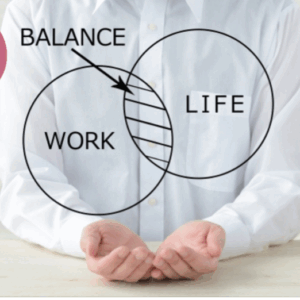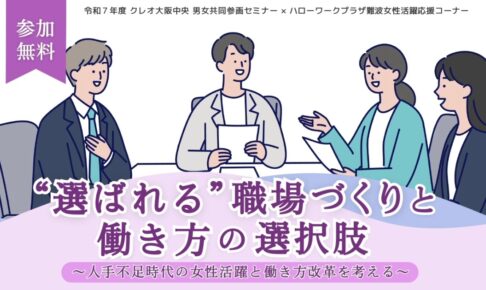男性が多い職場とされる建設会社で、建築の専門家として活躍しながら、子育て・介護を経験してきた藤岡慶子(ふじおかけいこ)さん。
活躍する女性リーダーが有志で設立した「万博サクヤヒメ会議」をとおして、ウェル・ビーイングな社会の実現を訴え、また、都島区長として地域の未来を描く藤岡さんに、その挑戦と展望をお聞きしました。
目次
1.理工系女性として活躍した会社員時代
①大学卒業後、建設会社に入社し一級建築士として働きながら、出産、育児、介護を経験されましたが、直面した困難や、その解決方法などについてお聞かせください。
小学生の頃、高度経済成長期に、たくさんの建物や街ができていく様子を目の当たりにしたことをきっかけに、建築分野に興味を持つようになりました。大阪大学の建築工学科に進学し、学生時代は男女の差を意識することなく過ごしていました。
しかし、その後の就職活動では性別の壁に直面しました。当時は「男女雇用機会均等法」の施行前で、女性の採用数がきわめて少ない状況でした。それでもあきらめずに、ようやく見つけた建築会社に一般職として採用されました。
その後、雇用機会均等法が施行され、総合職へ転換。念願だった建築士としてやっと働くことができるようになりました。しかし、最初はなかなか仕事を任せてもらえず、退職を考えたこともありました。そんな時、父から「社会はこれから変わる、もう少し待ちなさい」と励まされ、それを信じて建築関係の勉強を続けた結果、徐々に大きな仕事を任されるようになりました。父の助言に感謝しています。
結婚後は、仕事と家事、育児の両立が本当に大変でしたが、夫や保育園、地域の方々のサポートのおかげで乗り越えることができ、介護においても同様に多くの方に助けてもらいました。
②建築士としての経験の中で、一番心に残っているエピソードをお聞かせください。
特に印象深かった仕事のひとつに、神戸の社宅を設計したことがあります。コンクリート打ち放しのおしゃれなデザインに、真ん中に中庭を作り、シンボルツリーを植えました。のちに起きた阪神・淡路大震災では、その社宅は倒壊を免れ、中庭が地域の交流の場になったと聞き、「この仕事をして良かった」と強く思いました。
また、明石駅前の再開発事業にも携わる機会があり、明石市の街の発展に貢献することができました。
建築やまちづくりを通じて社会に貢献できた喜びは、今もなお心に残っています。
③理工系女性として苦労した点について、また理工系分野で働く女性へのアドバイスをお願いいたします。
建設業界は“男社会”だったので、働くうえで「女性だからしなくていい」と言われることが一番つらかったです。性別によって仕事の範囲が決まってしまうと、活動の幅が狭まってしまいます。今は個性を重視する時代であり、無意識の男女バイアスをなくすことがとても重要だと考えています。
建築というのは、人が空間の中でどのように心地よく過ごすかということをデザインする仕事です。そのため、女性ならではの視点や感性を活かすことができる、女性が活躍できる分野だと考えます。建築分野をはじめ、理工系分野に女性がどんどん進出していくことで、社会全体がより豊かになると思っています。

建設会社勤務時代
2.区長としての「女性活躍」と「地域活性化」
①公募で都島区長に就任された経緯についてお聞かせください。
区長になる前の2年間は、大学院で様々な組織の共創による新しい価値の創造や社会の課題解決について学びました。大学院への進学を決めたのは、子育てや介護がひと段落した時期であり、またコロナ禍で人と会うこともできない時期に立ち止まっていろいろ考えた結果、勉強したいと思いました。
その後、区長就任を志したのは、大学院で得た知識や視点に加えて、これまでの仕事や活動で得た経験など、様々な分野で培ってきたものが、自治体運営に活かせるのではないかと考えたためです。
②都島区長として、地域の活性化のために取り組んでいることをお聞かせください。
現在、都島区では「まちづくりビジョン2040」を策定しようとしています。都島区には三方が川に囲まれ緑豊かな環境に住宅地が広がり、他方、京橋地区など、東の玄関口としてこれから再開発が進んでいくエリアがあります。こうしたまちの資源や特徴を捉え、今後のまちづくりに生かしていくための指標を示し、都島区にかかわる方々との共創によって、よりよいまちを創っていくという取組です。
また、2025年の大阪・関西万博に合わせて、「みやこじま未来EXPO」と題し、都島区の新しい魅力づくりやまちの新たな可能性を広げていく仕組みづくりに取り組んでいます。人が来ることで街は変化していきます。施設や公共空間を整備するだけではなく、そこに人が集まり、活用してもらうことが大切で、その仕組みを検討していきます。
③現在の大阪市の女性活躍状況をどのように見ていますか。
大阪市職員における女性の管理職登用は進んでいると考えます。例えば都島区役所では、課長代理級以上27名中14名が女性、さらに副区長も女性です。民間企業では職種による差異はあるものの、全体として女性活躍は進んでいます。
しかしながら、大阪は首都圏に比べて女性が流出する傾向にあります。その背景には性別役割分担意識が、まだ根強く残っていることもひとつの要因ではないでしょうか。この“無意識のバイアス”をなくすことが女性活躍推進に向けた根本的な課題だと考えています。行政が率先して意識改革に取り組んでいくことが必要です。
例えば、少子化対策と女性活躍は、相互に関連する重要な課題です。子育てや介護は女性だけの役割ではなく、男性も一緒に協力し合う社会を実現しなくてはいけません。大阪市では、ひとり親支援なども充実していますし、都島区では、これから親になる方(プレパパ、プレママ)向けの講座など身近な意識啓発に努めており、新しい世代を支える取組も進めています。こうした取組を通じて、一人ひとりの個性が尊重される、包摂的な社会の実現をめざしています。
3.誰もが輝く社会をめざして -万博とサクヤヒメ会議の取組-
都島区長としての公務以外に、「万博サクヤヒメ会議」のメンバーとして、大阪・関西万博会場で「オオカミプロジェクト」に関わったことについてお聞かせください。
大阪商工会議所が創設した「大阪サクヤヒメ表彰」は、企業活動や文化的活動において活躍する女性リーダーを表彰する事業で、2016年度に始まり、5年間で227名が表彰されました。私はその第1期で、前職の建設会社の時に受賞させていただきました。
2019年に大阪で万博が開催されることが決定し、サクヤヒメ表彰の受賞者仲間がともに、2025 大阪・関西万博について共に考え活動する場として「一般社団法人万博サクヤヒメ会議」を設立することとなりました。サクヤヒメ会議では、女性が活躍しやすい社会や、誰もが心身ともに健康で幸せに暮らせる未来をめざして、さまざまなイベントや情報発信に取り組んでいます。
子どもたちの笑顔と元気を応援する「元気のぼりプロジェクト」では、万博会場で色とりどりのこいのぼりを製作したり、また、中学生とともに未来の働き方を考える「未来シンポジウム」などのイベントを開催し、どちらもたくさんの反響(参加者の喜びの声や新聞掲載)がありました。

大阪ヘルスケアパビリオンにて「オオカミプロジェクト」作家とのトークショー
また、大阪ヘルスケアパビリオンの内外に「オオカミベンチ」というアート作品を設置するプロジェクトも行いました。このオオカミベンチには、「女性活躍」という言葉が必要なくなるほど、誰もがウェル・ビーイングに生きることができる社会を実現したいという思いが込められています。多彩な10体のオオカミベンチには、会期中毎日たくさんの来場者が座り、また、パビリオンで作家のトークショーを開催し、年齢や性別を問わず多くの来場者の注目を浴びました。オオカミベンチは万博終了後、全国各地へ旅する予定で、作品に触れることを通して、社会が少しずつ優しく変わっていくきっかけにしたいと考えています。
4.自分らしく生きるために –日々のエールと大阪市への夢-
①多忙な日々のリフレッシュ方法や、モチベーションを保つ方法を教えてください。
仕事や様々な活動を行う中で落ち込むこともありますが、読書や街に出るなど、別のことをしてリフレッシュしています。自分をニュートラルな状態にすることで、新しい視点を持ち立て直すことができます。また、人生の出来事にはすべて意味があり、嫌なことがあったときは立ち止まることで何かが生じると考えています。
大事にしている言葉は「三方よし」。自分よし、相手よし、社会よしという商人の言葉で、自利利他の精神を意味します。人や社会のために一生懸命やっていると、何か自分に返ってくるということを信じています。
②最後に、期待する「未来の大阪市」はどのようなものでしょうか。
未来の大阪市に期待することは、日本の女性活躍ランキングで1位になってほしいということです。
日本は、世界経済フォーラムが発表するジェンダーギャップ指数において、非常に低い順位にあります。そのため、大阪市はこの順位を牽引して向上させていく力となってほしいと思っています。
ジェンダーギャップ指数で高い順位である北欧は、社会的なバイアスがあまりありません。社会保障や福祉制度が整っていることに加え、失敗してもやり直すことができるエネルギーがあるようです。
大阪市においても今後、意識や行動など社会的な変革を通じて、「女性活躍」という言葉がなくても一人ひとりの個性が輝くウェル・ビーイングなまちとなることを期待しています。

略歴
大阪大学工学部建築工学科を卒業後、建設会社に一般職として入社。
男女雇用機会均等法施行後、社内制度改正に伴い総合職となり建築設計部所属。以来、数多くの建築・まちづくり事業に携わり、第三者主催による建築・まちづくりプロジェクト表彰事業受賞歴多数。
平成28年 活躍する女性ロールモデルとして大阪商工会議所主催顕彰事業「大阪サクヤヒメ表彰」を受賞。
受賞者有志が設立した任意団体「万博サクヤヒメ会議」、「大阪サクヤヒメSDGs研究会」に参画し、まちづくり活動を実施。チームで取り組んだ「はぎれエコバックプロジェクト」はソーシャルプロダクツアワード2021を受賞。
令和3~4年度 大阪府まち・ひと・しごと創生推進審議会委員。
令和5年3月 立教大学大学院・21世紀社会デザイン研究科・比較組織ネットワーク学前期博士課程修了。
令和5年3月 建設会社退職。
令和5年4月 都島区長に就任。