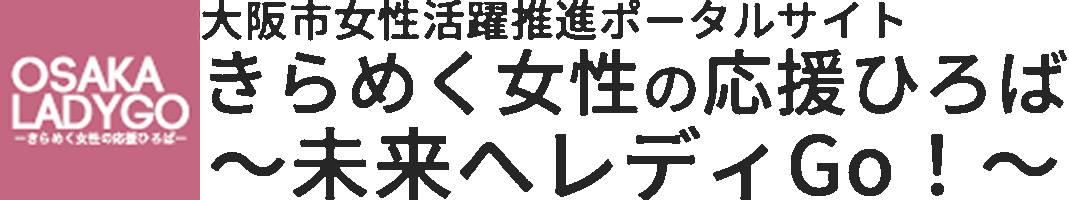公益社団法⼈全国鉄筋⼯業協会では、平成30年⼥性活躍推進ワーキンググループを発⾜させて以来、男⼥問わず働ける職場環境の改善や⼥性技能者及び女性技術者に対する男性の意識改⾰等を図り、担い⼿の確保・育成に向けた様々な取組を⾏っておられます。
⼥性職⼈の採⽤により、男性主体だった業界に⼥性の視点や感性が加わり、新たな気付きや顧客満⾜度の向上がますます期待されています。
当記事では、公益社団法⼈全国鉄筋⼯業協会会長岩田正吾(いわたしょうご)氏が代表者を務める正栄工業株式会社で活躍中の中村奈々(なかむらなな)さんにお話を伺いました。

目次
女性鉄筋技能職人としてのキャリア
私は中学校を卒業後、働きたいと思いアルバイトで工事現場の仕事をしていました。もともと体を動かすことが好きで、体を使った仕事を希望していました。ご縁があり弊社の副社長と出会い、正社員として、そして、女性初の技能者として17年前に入社することができました。
入社後17年が経ち、今では鉄筋工事のスペシャリストとして建築、土木建設の骨格である鉄筋加工と現場施工を担っています。例えば、一般的な建築物やマンション、物流センターなど、万博のパビリオンの鉄筋の組み立ても行いました。
力のいる仕事で、四季のある日本ではきついと感じる時もありますが、一生続けたい仕事と素晴らしい会社に出会えたことには感謝しています。

28歳妊娠がわかり、シングルマザーになる決断
現場の仕事も順調で、目標としていた職長(現場の長)として活躍していこうと思った矢先に妊娠が発覚しました。一瞬どうしよう…と不安になりましたが、妊娠を母に告げると「授かった命を大切にしなさい。産みなさい!」と背中を押してくれ、母の一言でシングルマザーになる決意が固まりました。
ひどいつわりはなかったのですが、いつもできることがなんだかできない、睡魔が襲う、気持ちが不安定など、妊娠を機に体の変化を確実に感じていました。そこで、社長に妊娠したことを告げると、「そうか!おめでとう!!安全帯をつけるし、現場仕事はもう無理じゃないか。」と言われました。力仕事はやめて、鉄筋の加工場で働きましたが、空気が悪く、体もついていかず休みがちになり、妊娠4ヶ月目で産休に入ることにしました。早くも無給になったわけですが、それほど不安はなく穏やかな気持ちでマタニティライフを過ごしていました。
そして、無事に元気な女の子を出産し、産後3ヶ月で職場復帰をしました。
復帰する際、子育てへ不安はありましたが、転職が頭をよぎることは全くありませんでした。産休・育休中も同僚によく連絡を取っていましたし、会社も私の復帰を待ってくれていたので、他にやりたいことがあるわけでもなく、保育園が決まったのと同時に迷わず復職しました。
しかし、現場は朝が早く朝5時には家を出て、帰宅は19時ごろになります。
保育園へ娘を送ることができず、夜も保育園のお迎えにも間に合わないので、娘の送り迎えは母に頼る日々がスタートしました。母は仕事をしながら家事全般もしてくれていたので、本当に助かりました。
娘の母乳は生後1ヶ月でやめており、夜泣きもしない子で、夜はぐっすり寝てくれるのが助かりました。仕事のある平日や土曜日は娘との時間は限られたものでしたが、帰宅後、娘の笑顔には癒される毎日でした。
母が認知症と診断
あんなに元気に仕事をしながら、孫の世話も熱心にしてくれていた母が、2020年ごろから一気に物忘れが進み、アルツハイマー型ではないものの認知症と分かりました。子どもはまだ2歳でどうしたらいいのかこの先が不安でした。
母が保育園のお迎えに行ってくれた帰り道に娘と二人で迷子になり、自宅まで帰れなくなったこともありました。今まで当たり前にできてきたことができないことが多くなってきました。
そこで、母に頼りすぎはよくない、母の負担も多過ぎると思い、働き方を変えてもらえるか会社に打診しました。現場ばかりの勤務でしたが、事務所勤務(積算作業)と現場勤務の半々の仕事内容にしてもらい、家庭への比重を昔より多くしました。事務所勤務の時は自宅にも早めに帰れるので、家事育児の時間も取りやすくなりました。

娘も小学校1年生に。おばあちゃんをサポート
今年の春、娘は小学校1年生になりました。おばあちゃんの認知症が進んでいることを娘も理解しているので、おばあちゃんをいろんな面でサポートしてくれ、とても助かっています。
母は今まで当たり前にできていた洗濯も、洗濯機を回していたことさえ忘れてしまうようになりました。洗濯機の中に洗濯物が1日中入ったままということもありましたが、娘が「おばあちゃん、洗濯機が止まったから洗濯物干しや!」とひとこと声をかけてくれるようになりました。たったひとことでも本当にありがたく思います。母は孫にそう言われたらハッと気づき、洗濯物を干してくれています。
今後の不安は、母の認知症がもっと進むことです。そうなれば自宅ではなく、施設に入れることも考えなければなりません。家事育児を母に頼ることもできなくなります。また、小学生の娘を長時間一人にすることにも躊躇してしまいます。

育児と介護が同時に直面しているダブルケア状態
まだ母は本格的な介護が必要ということではないですが、近い将来そのような状況になるのではという不安は大きいです。
母は今や料理もできなくなってきました。認知症が進んでいることは確かです。
娘が小学生になり、この夏の初めての夏休みがもうすぐやってきます。今からとても不安です。
保育園時代は夏休みも関係なく預けることができ助かっていましたが、小学生になると夏休み期間中も学童保育はあるものの、お弁当を持参して1日中学童に通わせるのは、親も子も負担を感じてしまいます。
弊社はゴールデンウィーク中、長期休みになることがありますが、正直なところ5月の長期休みは私には必要なく、むしろ夏休みに長く休める方がありがたいと思っています。夏の現場は過酷な暑さとの戦いなので、夏休みに長期休暇を取ることができれば身体への負担も少なく、家庭も守れるので私にとってはありがたいです。
職場には総務や経理の事務職員に女性はいるので、相談をしたりもします。全く同じ境遇の人はいませんが、先輩ママからのアドバイスはためにもなりますし、今の私の不安な状況を聞いてもらえるだけでも心の支えになっています。
今後の目標と願い
私は子どもを持ってから人に対して優しくなれたと思います。出産前は外国人技能実習生や新人にもイライラしていることが多かったと感じています。今は新人にも優しく丁寧に指導できるようになり、対応の仕方が変わりました。
今後も同僚と良い関係を築き、この会社で一生働くことが目標です。

そして、女性社員がもっと増えることを望んでいます。外国人の技術者で工場で働く女性は2名いますが、もっと仲間を増やして仕事に取り組みたいです。一緒に業務に当たりたいので、現場で働く女性が増えてほしいです。私が先輩社員として、女性鉄筋職人たちのロールモデルとなれたら嬉しいです。

プライベートの望みは、人生楽しく、家族で楽しく暮らしていきたい、ただそれだけです。
土曜日も仕事があるので、娘が「今日学校お休みなのに、お母さんは仕事に行くの?お母さん行かないで!」と言ってくる時は後ろ髪を引かれる思いで自宅を出ます。帰ってきた時はすでに外も暗いですし、一緒に外で遊べないので残念な思いをさせてるなと感じることがあるので、休みの日は思いっきり娘と楽しむようにしています。
一緒に出かけたり、友達ぐるみで公園へ遊びに行ったり、買い物やご飯を食べに出かけたり…私は小学校・中学校時代の友達と今でも仲がいいので、その同級生たちともよく子連れで遊びます。
娘との思い出もたくさん作っていきたいです。そして、娘にも母にも不自由なく生活させてあげたいです。

最後に岩田正吾社長よりメッセージ
中村さんは、まるで娘のような存在です。初めて出会ったのは彼女がまだ10代の頃で、元気がよく、やんちゃそうだという印象を受けました。今では母親となり、本当に穏やかで優しい女性になったと感じています。仕事に対しては常に真面目で、芯の強いしっかり者の社員です。
弊社に入社してから、もう17年が経ったかと思うと、本当にあっという間でした。彼女は責任感が強く、過酷な現場でも力を発揮してくれています。将来的に女性の職人が増えていく中で、彼女がずっと望んできた「女性鉄筋職人のための優しい現場づくり」をぜひ実現してほしいと願っています。

弊社は社是として掲げる、西郷隆盛の言葉「敬天愛人」を念頭に置き、経営理念は「仕事を通じて人間形成を図る」ことです。常にこの言葉と理念を胸に、社会に貢献する企業道を貫き、企業としても人としても日々研鑽を積み重ねてきました。1953年の創業以来、信頼と実績を築いてきたことが、今の正栄工業を支えていると自負しています。
中村さんにはこれからも、仕事には全力で取り組み、しっかり遊ぶときは遊ぶという、メリハリのある人生を歩んでほしいと願っています。鉄筋工事を通して社会に貢献し、家族にも誇れる存在として今後も活躍してくれることを期待しています。
また、彼女のように出産後も働き続けられる女性職人が増えることを強く望んでいます。そして、中村さんが目指す「女性だけの現場づくり」もぜひ実現してほしいと願っています。
現在、日本では少子高齢化と人口減少の影響により労働人口が急減し、建設技能労働者数も今後大幅に減少すると見込まれています。
これは国家的な課題と言えるでしょう。そうした中、ICT化やロボット化が急速に進み、建設業界を取り巻く環境も大きく変化していますが、建物の骨組みとなる鉄筋工事の多くは、依然として職人の手作業に頼っています。
地震大国である日本において、安全・安心な建物づくりにおいて鉄筋工事は極めて重要であり、優れた職人の存在は不可欠です。だからこそ、男女の別なくすべての人が働きやすい環境を整備することが、女性活躍の推進と若手の入職・育成につながる鍵になると考えています。そのためにも、建設業全体として託児支援や拘束時間の見直しといった課題に取り組む必要があります。これらの課題解決には、国や自治体の支援も不可欠です。
私自身も女性職人にとって働きやすい環境づくりを今後も模索し続けていきたいと考えています。